投稿日:2020年12月9日 | 最終更新日:2021年7月2日
睡眠時無呼吸症候群
睡眠中に呼吸が止まる2つのタイプとは?
睡眠中に呼吸が止まってしまう原因は大きく分けて2つあります。
1つ目は、空気の通り道である上気道が物理的に狭くなり、呼吸が止まってしまう閉塞性睡眠時無呼吸タイプ(OSA)。
2つ目は、呼吸中枢の異常による中枢性睡眠時無呼吸タイプ(CSA)です。
閉塞性睡眠時無呼吸タイプ(OSA)
喉や気道が塞がってしまうタイプ
上気道に空気が通る十分なスペースがなくなり呼吸が止まってしまうタイプです。
SAS患者さんのほとんど、9割程度がこの閉塞性睡眠時無呼吸タイプ(OSA)に該当します。
上気道のスペースが狭くなる要因としては、首・喉まわりの脂肪沈着や扁桃肥大のほか、舌根(舌の付け根)、口蓋垂(のどちんこ)、軟口蓋(口腔上壁後方の軟らかい部分)などによる喉・上気道の狭窄が挙げられます。
これには、骨格とその中におさまる解剖学的な組織の量が関係します。
元々大きい骨格であれば多少太ったとしても、つまり組織の量が増えても、上気道を狭める可能性はそう高くはありません。しかし、例えば元々小さい骨格の場合はどうなるでしょう?
上気道のスペースが圧迫されて狭くなり、元から上気道のスペースが少ない場合にはさらに閉塞しやすい状況になるわけです。
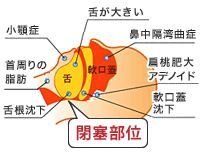
横向きになるといびきが止まる!?
「仰向けに寝るといびきをかくのに、横向きになるといびきをかかない」のは、仰向けで寝た時に気道が狭くなっている証拠。特に仰向けの場合は舌の付け根(舌根)などが上気道に落ち込みやすくなります。睡眠中は筋肉が弛緩するので、ただでさえ無呼吸が起こりやすい状態になるのです。
上気道に十分なスペースがあるときには問題ないのですが、上気道が閉塞してくると狭い隙間を空気が通ろうとするので、音、つまり「いびき」が生じます。そして上気道が完全に塞がれてしまうと空気が通る隙間がなくなり、「無呼吸」になるわけです。
電車の中や会議中などで椅子に座った状態でもいびきをかいてしまうとしたら、要注意です。
中枢性睡眠時無呼吸タイプ(CSA)
脳から呼吸指令が出なくなるタイプ
脳から呼吸指令が出なくなる呼吸中枢の異常です。睡眠時無呼吸症候群の中でもこのタイプは数%程度です。
肺や胸郭、呼吸筋、末梢神経には異常がないのに、呼吸指令が出ないことにより無呼吸が生じます。OSAと違い、気道は開存したままです。OSAの場合は気道が狭くなって呼吸がしにくくなるため一生懸命呼吸しようと努力しますが、CSAの場合は呼吸しようという努力がみられません。
CSAに陥るメカニズムは様々ですが、心臓の機能が低下した方の場合には30-40%の割合で中枢型の無呼吸がみられるとされています。
この中で、閉塞性睡眠時無呼吸タイプ(OSA)の原因となる可能性があるのが抜歯矯正です。

抜歯矯正をすると、口腔内は成人なのに歯列が中学1~2年の歯並びの大きさになってしまう。
したがって、舌の置き場所も狭くなるのでいびきをかきやすくなったり、舌根沈下による睡眠時無呼吸症候群(すっかり新幹線の運転手の居眠りで有名になった病気)を誘発する恐れもあると言われてます。
まさか、矯正治療のために歯を抜いて将来睡眠時無呼吸症候群で苦しむとは想像できませんよね。
しかし、歯科医師からみればあり得ることだよね、です。
深い知見があれば、睡眠時無呼吸症候群と不正咬合の矯正治療が有効なことが示唆されます。
総合的な診断が可能な、当矯正歯科医院に御相談下さい。